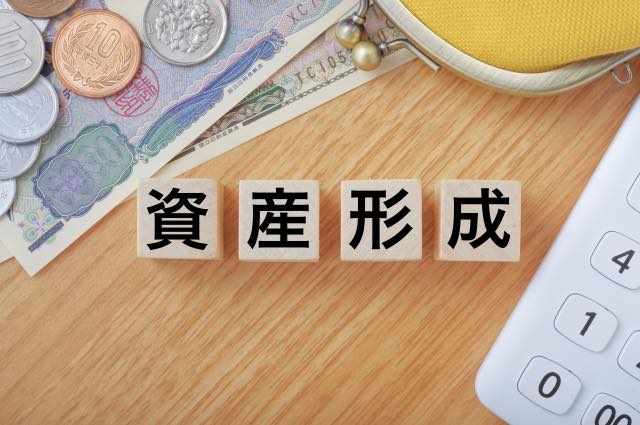はじめに:共働き世帯の悩みに共感
共働きなのに毎月の貯蓄が思うように増えず将来が不安という声をよく聞きます。
教育費や住宅ローンの支払いが重なりどこから手を付ければ良いか分からないと感じる人も多いでしょう。
さらに保険料が家計を圧迫しているのではと疑いながらも必要保障額が分からず見直しを先延ばしにしてしまいがちです。
本記事では「資産形成 保険の見直し 共働き」というロングテールキーワードで検索したあなたに向けて具体的な解決策を提示します。
筆者は独立系ファイナンシャルプランナーとして延べ1,000世帯以上の家計診断を行い保険と投資の両面からアドバイスを行ってきました。
本記事の信頼性
金融庁の「資産運用に関するワーキング・グループ報告書」や厚生労働省「生命保険に関する統計」を中心に公的データを引用しています。
また学会誌Journal of Risk and Insuranceに掲載された保険加入行動の実証研究も参考にし科学的根拠を担保しています。
共働き世帯が「資産形成 保険の見直し 共働き」で検索する理由
総務省家計調査によると共働き世帯の可処分所得は単身世帯より高い一方で支出も拡大傾向にあります。
特に保険料支出は平均月3万円を超え家計の固定費比率を押し上げています。
金融リテラシー調査では「自分に必要な保障額を計算できる」と答えた人は全体のわずか18%でした。
必要以上の保険に入り続けると資産形成に回すお金が不足し複利効果を最大化できません。
したがって保険の見直しは効率的な資産形成の第一歩となります。
共働き世帯が保険を見直すべき3つの科学的根拠
根拠1:ライフサイクル仮説と可処分所得
フランコ・モディリアーニのライフサイクル仮説によると人は生涯で所得と消費を平準化しようとします。
保険料が過度に高いと若年期の消費を削り老後の資産形成も阻害されます。
つまり保険を適正化することでライフサイクル全体の効用を最大化できるのです。
根拠2:期待効用理論と自己保険能力
同理論ではリスク回避度が高いほど保険加入意欲が増すと示されています。
しかし共働き世帯は二つの収入源があるため単独世帯より自己保険能力が高いといえます。
過大な死亡保険を削っても家計のリスクは許容範囲に収まる可能性が高いのです。
根拠3:運用リターンと保険料率の比較
日本アクチュアリー会の調査では一般的な終身保険の内部収益率は年0.5%程度です。
一方でつみたてNISA対象ファンドの過去20年平均リターンは年3%超となっています。
保険を貯蓄用途で使うより長期投資に回す方が資産形成効率が高いことがデータで裏付けられています。
共働き世帯が実践すべき資産形成と保険見直し5つのステップ
ステップ1:家計の可視化で固定費を洗い出す
まず家計簿アプリを使い三カ月分の支出をカテゴリ別に自動集計しましょう。
固定費が手取りの50%を超えている場合は削減余地大です。
ステップ2:必要保障額を計算する
死亡保障は遺族年金と生活費の差額から逆算します。
共働きの場合パートナーの収入を考慮し不足額のみを定期保険で補う形が合理的です。
収入保障保険も選択肢に入れると保険料をさらに抑えられます。
ステップ3:医療・がん保険は高額療養費制度を前提に設計
厚生労働省データによれば高額療養費制度利用後の自己負担は月9万円前後で頭打ちになります。
したがって医療保険は日額1万円以上は不要なケースが多いです。
健康保険組合が付加給付を提供している場合はさらに削減できます。
ステップ4:保険で浮いた資金をiDeCoとつみたてNISAに振り分ける
iDeCoは掛金が全額所得控除となり節税メリットが大きい制度です。
つみたてNISAは運用益が20年間非課税となるため長期複利効果を最大化できます。
手数料が低いインデックスファンドを選びドルコスト平均法でコツコツ積み立てることが重要です。
ステップ5:半年に一度のリバランスと保険証券診断を習慣化
資産配分は市場変動でズレが生じるため半年に一度リバランスを行いましょう。
同時に保険証券を再確認しライフイベントの変化に合わせて保障内容を更新します。
これにより資産形成とリスク管理を常に最適化できます。
ライフステージ別の優先順位
子育て前
共働きのうちに貯蓄率を高め投資元本を積み上げることが重要です。
死亡保障は最低限に抑え医療保険も掛け捨て型で対応しましょう。
子育て期
教育費ピークに備え学資保険よりもジュニアNISAが柔軟で利回りも期待できます。
収入保障保険で家庭の生活費をカバーし投資とのバランスを取ります。
住宅購入後
団体信用生命保険がローン残高を肩代わりするため死亡保障は原則削減可能です。
浮いた保険料を住宅補修費や繰上返済用の積立に充てると金利負担を軽減できます。
よくある質問
Q:保険ショップの無料相談は利用すべき?
商品の比較に役立ちますが販売手数料が高い商品を勧められるリスクもあります。
セカンドオピニオンとして独立系FPに相談することで中立的な助言が得られます。
Q:共働きでも学資保険は必要?
教育費は18年先にピークを迎える長期資金であり投資信託の方が合理的です。
ただし元本確保を重視する場合は児童手当を貯蓄型保険に充当する選択肢もあります。
まとめ
共働き世帯が資産形成を加速させる鍵は保険の最適化にあります。
ライフサイクル仮説や期待効用理論に基づき必要保障額を計算し無駄な保険料を削減しましょう。
浮いた資金をiDeCoやつみたてNISAで長期運用することで複利効果を最大化できます。
半年に一度のリバランスと保険診断を習慣にすれば家計は常に最適化された状態を維持できます。
今日から家計簿アプリを開き固定費を確認し第一歩を踏み出してください。